読書した中で心ひかれた文章を少しご紹介します
「 信と不信の文学」
ユダ あるいは虚構としての人間
笠原芳光
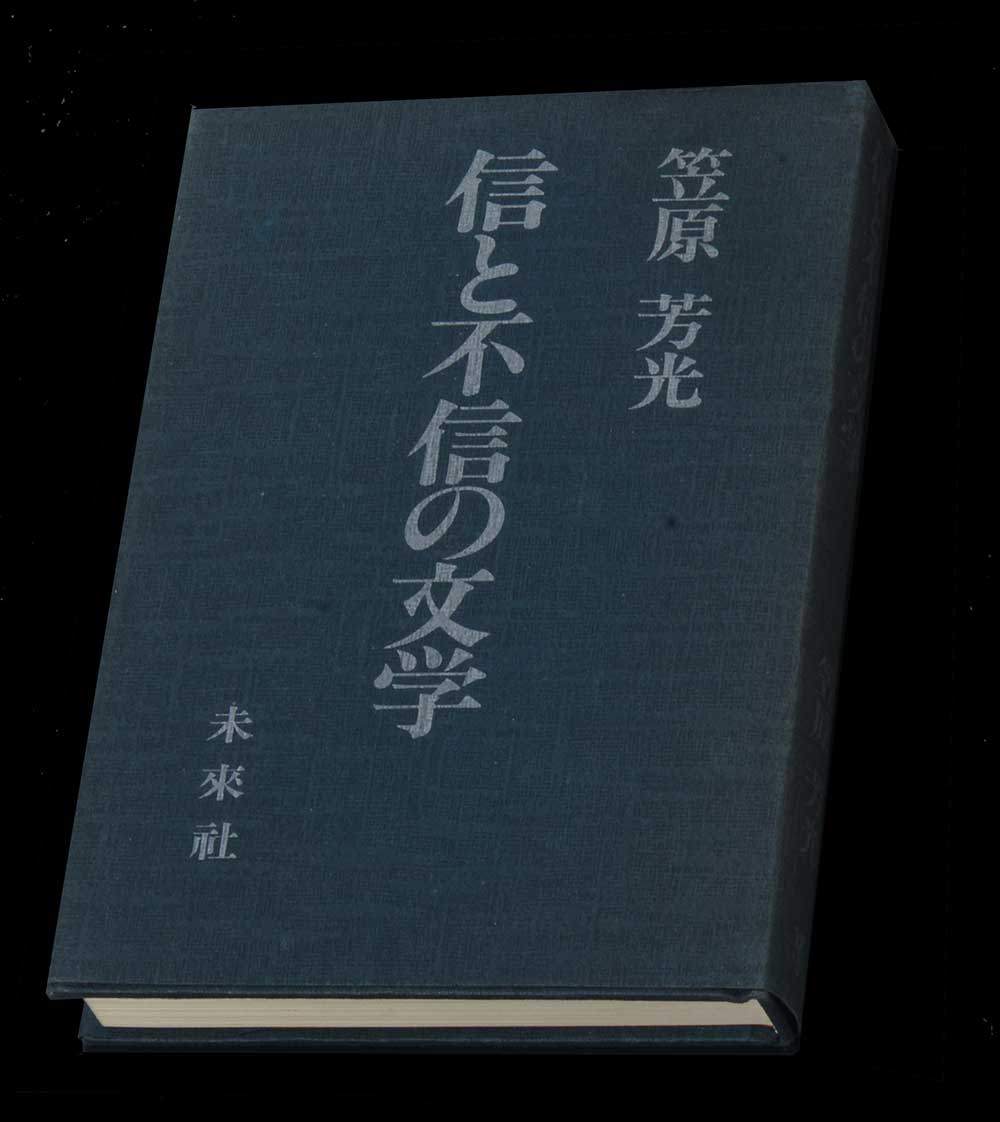
1981年11月15日 第1刷発行
目次
|
「ユダあるいは虚構としての人間」より一部抜粋
段落ごとに一行開けました
|
2019.5.1

読書した中で心ひかれた文章を少しご紹介します
「 信と不信の文学」
ユダ あるいは虚構としての人間
笠原芳光
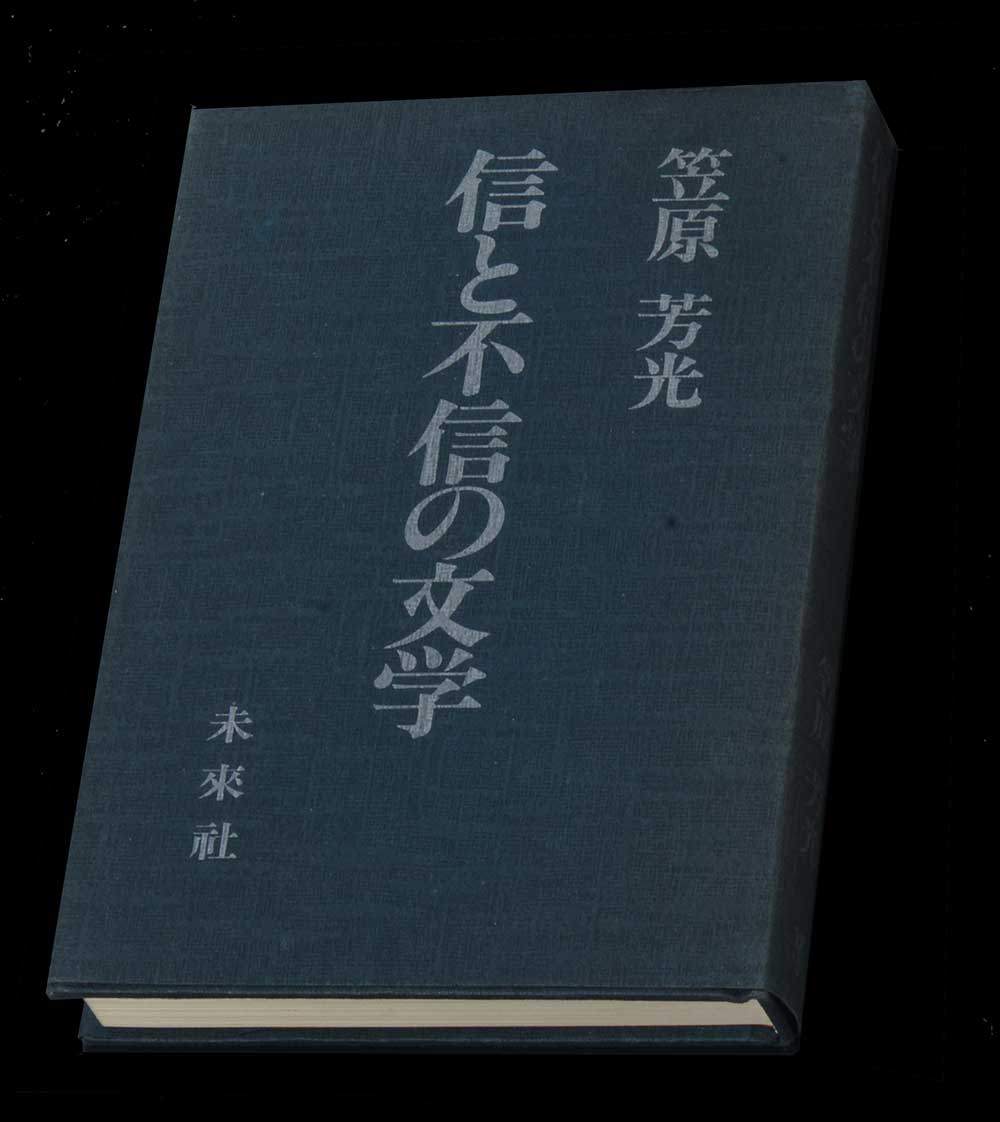
1981年11月15日 第1刷発行
目次
|
|
